日々の生活や仕事において、課題解決やアイデア創出が求められる場面が多々あります。その際に重要なのが、「具体」と「抽象」を自由に行き来する思考の柔軟性です。細谷功氏の著書『「具体⇔抽象」トレーニング』は、まさにこのスキルを鍛えるための指南書であり、私たちが思考力を高め、創造性を引き出すための道標を提供してくれます。本記事では、本書の内容を深掘りし、その魅力をお伝えします。
そもそも「具体」、「抽象」とは?
具体と抽象は、私たちの認識や思考における対象やアイデアの捉え方の2つの異なる側面を表しています。具体は詳細で具体的なものを指し、抽象は一般的な概念やアイデアを表します。
これらの2つの考えを活用することで、私たちは情報を整理し、問題を理解し、コミュニケーションを行い、あらゆる物事に対する理解を深めることができます。
そしてこれから紹介する「具体」と「抽象」を用いた思考法は、さまざまな場面で役立つものであり、抽象化は物事を整理し、新しい視点を発見するための基盤となるスキルです。一方、具体化は、抽象的な考えを実際の行動に結びつける力を指します。
具体⇔抽象の思考法がこれからの時代において欠かせない理由としては以下の点が挙げられます。
- 課題の明確化 具体的な事実と抽象的な視点をバランス良く使うことで、問題を正確に捉えることが可能になります。これにより、解決策を探るための確固たる土台が築けます。
- 創造性とイノベーションの促進 抽象的なアイデアを具体的な行動や実践に変換する力により、創造的なアプローチを採用し、新しい発想や革新的な解決方法を導き出すことができます。
- 効果的なコミュニケーション 具体と抽象の両方を自在に操ることで、相手との意思疎通がスムーズになり、考えや意見の共有がより分かりやすくなるため、より良い人間関係が構築できます。
具体と抽象を組み合わせた「具体→抽象→具体」という思考プロセスを活用することで、単なる表面的な問題ではなく、本質的な課題を深く掘り下げて解決できる力が養われます。これらの理由から、具体と抽象の考え方を知ることは重要であると言えるのです。
もう少し、「抽象」「具体」について深堀して説明させてもらいます。
抽象
「抽象」とは、具体的な要素や特定の対象から導き出されたもので、普遍的な概念やアイデアを表します。これは、個別の具体的な事例をもとにして、それらの共通する特性や原則を抽出した結果として生じます。
たとえば、「愛」や「自由」、「民主主義」といった概念、さらには数学の公式や科学理論が抽象的なものの例として挙げられます。これらは、具体的な事象から一般化された法則やパターンとして導かれ、多くの場合、言語や記号を用いて表現されます。
また、物事を整理したり、不要な要素を取り除いたり、範囲を決めたり、視点を高めたり、あるいは自分自身を客観的に捉えるといった行為は、基本的にはすべて抽象化の一形態であるといえます。
具体
「具体」とは、目に見えたり触れたりできるような明確な形や特徴を持った対象や現象を指します。これらは五感を通じて直接的に感じ取れるもので、認識しやすいという特性があります。
たとえば、「りんご」や「車」、「家」、「人」、「出来事」などが具体的な例と言えます。それぞれ個別の特徴や詳細があり、視覚や触覚、聴覚などの感覚を通じて理解できます。
また、具体化とは、曖昧だったものをよりはっきりと示すプロセスを指します。具体的には、選択肢や可能性を限定する、違いを明確にする、あるいは数値で表すといった行為が含まれます。
具体と抽象でデキる人材へ
『「具体⇔抽象」トレーニング』の冒頭で述べられているように、本書の目的は「具体⇔抽象の思考法を身につけることで、コミュニケーションにおけるギャップを解消すること」にあります。
そして私は本書を読んでみて、とりわけ「抽象」の概念を理解することがポイントであると解釈しました。
実際、コミュニケーションのすれ違いの多くは、話し手と聞き手の間で「抽象度」が異なることが原因だと思います。例えば、「小説だけが好きな人」に対して「本全般が好きなんだね」と解釈してしまう場合のように、抽象度が揃わないことで誤解が生じることがあります。
これからのコミュニケーションにおいては、以下のポイントを意識することが重要とされています。
- 抽象度の一致を意識する 自分の発言と相手の発言が同じ抽象度にあるか確認する。
- 意図的な違いの認識 抽象度に差がある場合、それが意図的なものであるかを検討する。
- 伝達の明確化 意図的な抽象度の違いがある場合、それが相手に十分伝わっているかどうかを考える。
抽象度という概念を理解しているかどうかは、選ぶ言葉の質や相手に正確に伝わるかどうかに大きく影響します。このようなスキルを磨くことで、互いの理解が深まり、コミュニケーションの質を格段に向上させることが可能になります。
まとめ
個人的な感覚論ではありますが、まるで抽象的であることが欠点であり、具体的であることが優れているかのように語られがちです。
しかし、実際には「具体」と「抽象」は単に視点の違いでしかありません。「細部を見るか」「全体像を見るか」といった違いに過ぎず、例えば「カップケーキ」と捉えるか「デザート」と捉えるかのようなものです。どちらが良い悪いという話ではなく、状況によって適切な視点を選ぶことが大切です。
例えば、飲食店のメニューに「チョコレートムース」という名前があれば、多くの人が一般的なイメージを共有できます。しかし、「滑らかな質感のチョコレートクリームを冷やし固め、ミントの葉を乗せて提供する、小さなガラス容器に収められたもの」と詳細に説明されていたら、かえってわかりにくいでしょう。これは具体的な情報を過剰に提供しすぎた例です。
具体的な視点と抽象的な視点は、状況に応じて使い分けるべきであり、そのためにはまず「具体と抽象には異なるレベルがある」という認識を持つことが重要です。この違いを意識することで、より効果的に情報を伝えることが可能になります。
そして、この「抽象と具体を行き来する」思考法こそが、これからの対話や意思疎通の基盤となるのです。
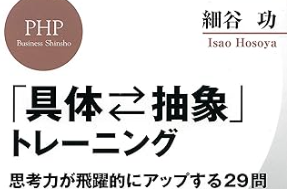


コメント