今後すべてのビジネスパーソンにプロジェクトマネージャーとしての力量が求められると思います。ここ10年ほどビジネス環境における状況の変化は加速度的であり、従来のルールでは対応できない事象が頻発しています。そんな中、既存のルールに判断基準を置き、目の前の仕事を処理していく業務能力は、無価値となりつつことは皆さんも感じられているところでしょう・・・
一方で目的と価値観に立脚し、自分の判断で物事を進めていくプロジェクトマネジメントの能力が一層求められるようになっています。
今回は「プロジェクトマネジメント」スキルの本質について語られている、「外資系コンサルが教える プロジェクトマネジメント」著:山口氏を紹介いたします。
目的の設定
プロジェクト運営において最も重要だとされるのが、明確な「目的」の設定です。
目的がしっかりと定められ、全員に共有されていることには、いくつかの利点があります。まず第一に、明確な目的を持つことで、プロジェクトの進行中に何らかの障害が発生した際、柔軟に代替策を講じることが可能になります。一方で、目的を見失い手段が目的化した場合、他の手段に切り替えることが難しくなり、行き詰まる恐れがあります。
次に、目的がメンバーに共有されていると、意思決定を行う際の指針となります。目的が共有されていない状況では、各メンバーが経験や直感に頼って判断せざるを得ず、方向性の統一が困難になります。その結果、プロジェクトマネージャーが都度、意思決定の修正を行う必要が生じ、効率を損なう可能性があります。
さらに、明確な目的はメンバーのモチベーションにも影響を及ぼします。仕事に意義を見出せない場合、情熱を持って取り組むことは難しいものです。目的を共有し、その重要性を全員に認識させることは、メンバーのやる気を引き出すためにも欠かせません。
これらの理由から、明確な目的を設定し、それをメンバー全員に浸透させることは、プロジェクトリーダーにとって重要な役割となります。また、目的を正確に理解し、それを誤解なく伝えるためには、プロジェクトオーナーとの間でしっかりと認識を合わせ、確認を取ることも大切です。
周囲の期待値をコントロールする
では、プロジェクトオーナーに対して「どのような認識合わせが必要か?」
本書では繰り返し「期待値のコントロール」の重要性について述べられています。理由は明快で、関係者の期待値を上回ることができれば「成功」、期待値を下回ってしまったら「失敗」だからです。
理想的な期待値の推移としては、初期段階では期待値を低めに設定し、プロジェクトの進行に伴い徐々に期待値を引き上げ、最終成果物が初期の期待を超えたところに着地するのが望ましいです。そのため、プロジェクトの初期段階ではオーナーの期待値が過剰に高まらないように注意を払い、懸念がある場合には可能な限り早い段階でそれを共有して期待値を抑える努力が求められます。「予想外に達成できませんでした」といった状況を避けるために、早めの対策を講じることが、プロジェクト全体の成功においても個人の評価においても重要です。
期待値をコントロールするうえで重要な要素は「時間」「コスト」「品質」です。
これらの各要素がプロジェクトが要求する水準に対してちょうど100%しか見込めない場合は、すんなり受け入れてはなりません。「この資源では戦えません、〇〇をください」と交渉すべきであると筆者は主張しております。
なぜそこまでこだわる必要があるのか、それは「成功も失敗もあらゆるプロジェクトの結果がリーダーに帰属するから」です。もう少しわかりやすくイメージを持ってもらうために私が職場で実施しているやりとりを紹介させていただきます。
私も例に漏れずですが、プロジェクトを任される際に「高めの期待値」をオーナーから押し付けられることが多々あります。最終的には私もサラリーマンなので飲み込むわけですが、初期段階でこちらが想定する「低い期待値」(資源が不足しているのでここまでが妥当という線引き)を必ずぶつけるようにします。そうすることによってあちら側の言い分を飲み込んだという「貸し=負い目」が生じます。この「負い目」をオーナーに持たせることによって、とある局面で追加の資源が欲しい際に使える「交渉カード」として切ることができます。
このように「低めの期待値」を見せることで、譲歩を引き出すためのカードを手に入れ、プロジェクトを有利に実行できるので、皆さんもぜひステークホルダーの期待値を意識したプロジェクトマネジメントを遂行してみて下さい。
メンバーには「行動」ではなく「目的」を伝える
メンバーから嫌われるマネージャーの典型例として挙げられるのが「マイクロマネジメントする上司」です。これをやってしまうとメンバーの社会的活動に対する動機づけを奪ってしまい、仕事に対するコミットメントが破壊されます。大事なのは「何をするのか」ではなく「何を達成したいか」を伝え、そのうえで「やり方」はメンバーに任せることです。「目的」の重要性は先述した通りですが、明確な目的地を伝えておけば、当初の想定通りに物事が運ばない局面で、「どうしようか?でも最終的にはあそこにたどり着ければいいのか」といった具合で迂回ルートを見出して目的地まで行く努力をするでしょう。その過程でメンバーなりの創意工夫があったり、上手くいった、行かなかったという反省があり、力量が伸びていくと思います。
一方で「行動」だけ伝えてしまうことは、「右・左」の指示だけでゴールまでたどり着こうとする手法と同じなので、想定外の事態が起きた時に目的地を知らないので臨機応変な対応ができないのです。
(とはいえ、力量が不足している人に対しては「目的」「行動」をセットで伝える必要があると思います)
メンバーの力量を踏まえた上で、できるだけ任せながらプロジェクトを動かすことが最適であるというのが筆者の主張です。
まとめ
ここまでお読みいただいた方には「プロジェクトマネジメント」スキルが「組織として成果を生み出す」どの業界でも活用できるスキルであることがご理解いただけたかと思います。
最後に質問です。皆さんは今後どんなスキルを身に着けたいですか?
①その会社で評価されるスキル
②その業界で評価されるスキル
③どの業種でも評価されるスキル
より広範な領域に対して結果を残したい、という方はぜひ今回ご紹介させていただいた「プロジェクトマネジメント」を手に取って、豊かで充実した仕事人生を一緒に目指していきましょう!
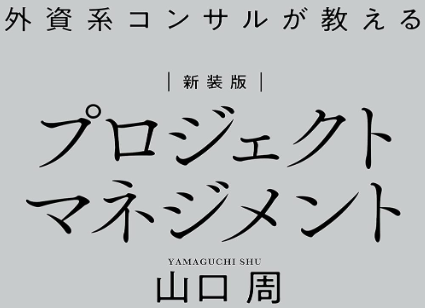


コメント